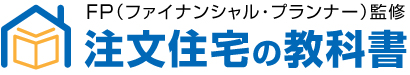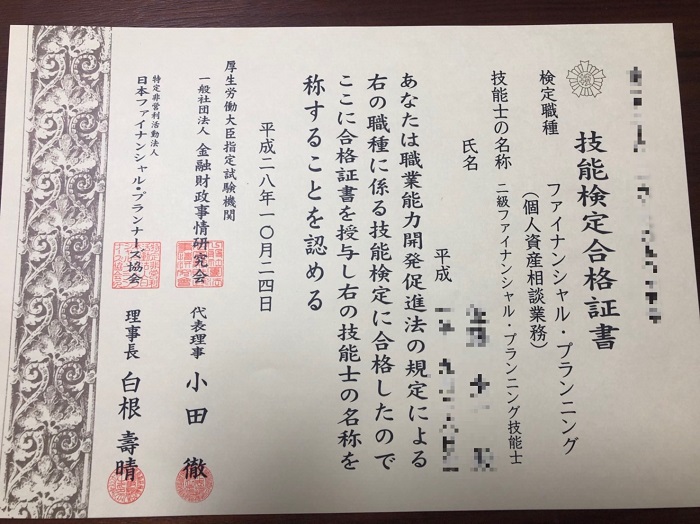家の新築や購入を計画されている方は、長期優良住宅という名称を耳にしたことがあると思います。
長期優良住宅とは、「長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅」のことで、法律によって認定された住宅をいいます。
ここでいう長期とは、おおむね3世代が引き継いで住み続けられる期間(100年ほど)をさしています。
しかし、具体的に「長期優良住宅にはどのようなメリットやデメリットがあるのか」「どうすれば認定されるのか」わからない、という方が多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、長期優良住宅のメリット・デメリットや認定の基準をわかりやすく解説します。
なお、本記事で紹介する長期優良住宅の紹介は、改正された令和4年10月1日の内容としています。
1.長期優良住宅とは
冒頭で述べたように「長期優良住宅とは、長い間良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅」、言い換えれば、住宅性能を向上させた長期の使用に耐える家のことです。
認定基準には、劣化対策や耐震性能など10の条件があり、これらを満たして申請・認定されることで「認定長期優良住宅」となります。そして、住宅ローンの金利や各種税制面での優遇措置が適用されます。
1-1.長期優良住宅の目的
しかし、なぜ長期優良住宅は税金や金利などが優遇されたり推奨されたりするのでしょうか。その目的は何でしょうか。
長期優良住宅の認定制度には、長持ちする家を建てることで、短期間での建て替えを抑えると共に、質の高い住宅を流通させ、新築・中古市場を活性化させる目的があります。さらに、省資源で自然環境を守るという時代背景もあります。
このように、近年では、「住宅をなるべく長持ちさせよう」という考え方に変わってきています。あなたも長期優良住宅にすることで、環境や家計に優しい家を目指してはいかがでしょうか。
2.長期優良住宅の優遇制度とメリット

長期優良住宅に認定されると、住宅ローン金利の優遇や減税など、いろいろなことがお得になります。
もし、あなたが長期優良住宅にするかどうかを悩んでいるのであれば、ここで解説するメリットに目を通しておくようにしましょう。
2-1.フラット35の金利が引き下げられる
長期優良住宅にすると、住宅金融支援機構のフラット35の住宅ローン金利よりも低い金利が10年間適用されます。
住宅ローンの金利は、わずかな差でも利子総額が大きく変わります。住宅金融支援機構の試算では、借入額3,000万円、返済期間35年で長期優良住宅にすると、一般的な住宅のフラット35に比べて、返済総額では74万円ほど安くなっています。
この差は大きいですね。金利を優遇してもらった分の費用をキッチンのグレードをいいものにしたり、家族のために貯金したりできます。
2-2.所得税あるいは住民税の控除額が増える
住宅の新築や購入でローンを利用すると、住宅ローン控除というものを受けられます。この控除は、所得税の還付あるいは住民税の減額という形になりますが、長期優良住宅の場合には、一般的な省エネ基準の住宅より控除額が多くなるのです。
具体的には、年末時のローン残高の0.7%が所得税あるいは住民税から13年間控除されるというものです。ただし、ローンの返済期間が10以上の場合に適用されます。
■長期優良住宅と省エネ基準住宅の住宅ローン控除比較(令和5年入居の場合)
| 住宅ローン控除 | 一般住宅(省エネ基準適合) | 長期優良住宅 |
| 借入限度額 | 4,000万円 | 5,000万円 |
| 控除期間 | 13年間 | |
| 控除率 | 0.7% | |
| 年間最大控除額 | 28万円 | 35万円(▼7万円) |
| 最大控除額 | 364万円 | 455万円(▼91万円) |
上表で、借入限度額というのは、住宅ローン控除を受ける際の年末時のローン残高の限度額のことです。
例えば、長期優良住宅の限度額は5,000万円ですが、仮に年末時のローン残高が5,000万円を超えていても、控除額は5,000×0,007=35万円となります。
一般的な省エネ基準適合の住宅と比べると年間で7万円、控除期間合計では91万円も違いますね。
2-3.住宅ローンを組まなくても優遇される:投資型減税
先の住宅ローン控除は返済期間が10年以上の場合ですが、返済期間が10年未満や自己資金で長期優良住宅を購入した場合に優遇されるものに投資型減税があります。ただし、令和5年12月31日までの入居に適用されます。
減税額は、床面積に45,300円/㎡を乗じた金額(上限650万円)の10%(上限65万円)をその年の所得税から控除するというものです。そして、控除しきれない場合は、翌年分の所得税からも控除されます。
例えば、床面積120㎡の場合。
控除対象額:120×45,300=5,436,000(<6,500,000)
減税(控除)額=5,436,000×0.1=543,600(<650,000) となります。
2-4.登録免許税が減税され:所有権保存登記、所有権移転登記
新築住宅が完成したら、所有権保存登記が必要になります。これは、「所有権をあなたのものにする」ことを登記するものです。
このとき登記に税金が発生しますが、一般住宅の登録免許税が、固定資産税評価額の0.15%に対して、長期優良住宅では0.1%に優遇されています。
たとえば、評価額3,000万円の住宅の場合、一般住宅では4.5万円、長期優良住宅では3万円となります。
また、中古住宅の場合(所有権移転登記)にも減税措置があります。一般住宅の0.3%に対して、長期優良住宅では0.2%になります。なお、長期優良住宅マンションの場合は0.1%になります。この登録免許税の減税は、令和6年3月31日までの取得が適用となります。
登録免許税の減税額はわずかかもしれませんが、住宅の新築や購入では、色々な初期費用が必要になります。後述するその他の減税と合わせると、大きな金額になるのです。
2-5.不動産取得税の減額
新築住宅の場合は、(固定資産税評価額ー特例控除額)×3%の不動産取得税が必要になります。この時の特例控除額も長期優良住宅の場合、優遇されます。
一般住宅:(固定資産税評価額-1,200万円)×3%
長期優良住宅:(固定資産税評価額-1,300万円)×3%
ただし、この適用には後述する長期優良住宅の認定基準以外に、床面積が50㎡〜240㎡などの条件があります。
また、令和6年3月31日までの新築が対象となります。なお、中古住宅の場合は、築年数によって控除額がかわりますので、詳細は各都道府県で確認してください。
2-6.固定資産税の減額期間が延長される
一般的な住宅の新築では、固定資産税=固定資産税評価額×1.4%×1/2(減額措置)となり、1/2の減額措置期間が3年間適用となっています。
しかし、長期優良住宅の場合には、減額措置期間が3年から5年に延長されます。また、一般的なマンションの場合の減額措置期間が5年であるのに対して、長期優良住宅の場合は同じく2年間延長されて7年間となります。
ただし、令和6年3月31日までの新築が対象になります。そのため、対象期間を間違えないようにしましょう。
2-7.贈与税の非課税枠が500万円増加
住宅の新築・購入に際して、両親や祖父母などから贈与を受ける場合、一般住宅の非課税限度額が500万円なのに対して、長期優良住宅の場合には、1,000万円となります。
国税庁:贈与非課税限度額
3.長期優良住宅のデメリット
以上で長期優良住宅のメリットを述べてきましたが、デメリットも存在します。具体的にどのような点になるのかを順番に解説します。
3-1.建設費用が高額になる
長期優良住宅の条件に当てはめるためには、後述する耐震や省エネルギーなどの認定基準に適合する仕様・工事としなければなりません。
当然、それらに当てはまる住宅を建設すると、費用は一般住宅に比べて2割程度高くなります。
「たくさん優遇されるからいいのでは」と思う方もいるかもしれませんが、減税などで優遇されたとしても金銭面の部分だけでは、プラスになることは難しいのです。
ただ、その後の生活の快適さや長期間の使用に耐えるコストパフォーマンスなどを考えると、その2割は決して高い金額ではありません。
せっかく夢のマイホームを建設するのであれば、こだわった長期優良住宅を建設してみてはいかがでしょうか。
国交省:長期優良住宅認定制度
3-2.申請や認定に時間と手間がかかる

長期優良住宅の申請や認定には、時間と手間がかかります。
まず、長期優良住宅申請書を、確認申請書とは別個に作成しなければならず、審査もそれぞれの手続きを踏まなければなりません。
また、それらの審査には、一般的に数週間から1カ月程度の期間を必要とします。これは、着工前に必要な手続きですから、それだけ完成までの期間が伸びるということです。
また、完成したら計画どおりに出来上がったことを所管の行政庁に報告しなければなりません。
3-3.定期的な点検が必要
長期優良住宅は、認定をもらい完成・報告しても、それで終わりではありません。その後も、定期的に点検を行い、記録を保存しておく必要があるのです。
そして、「長期優良住宅建築等計画書」の維持保全計画(後述の4-9を参照)を行わないと、最悪の場合認定の取り消しや還付金(減税)の返還をしなければいけません。
4.長期優良住宅の認定項目と基準
長期優良住宅に認定されるには、いくつかの条件を満たさなければいけません。具体的にどのような項目があるのかをここで解説します。
なお、長期優良住宅の適用基準は、2022年10月1日から新しくなりました。
4-1.構造躯体の劣化対策:劣化対策等級3
長期優良住宅は、数世代(3世代)にわたって長く住み続けられる家でなくてはいけません。そのため、きちんとメンテナンスを行えば、100年住めるような劣化対策を講じた構造躯体である必要があり、最高等級3の性能としています。
なお、以下の基準項目を含めて、具体的な内容は、後述の「優良住宅認定基準」を参照ねがいます。
4-2.耐震性(倒壊等防止):耐震性能等級3(木造2階建壁量計算時)
日本は地震が多い国であるため、耐震性に優れてなければいけません。
せっかく建てた3世代が住める家も、地震で倒壊してしまっては意味がありません。そうならないために、耐震性能は最高等級3に改正されました。
なお、耐震性能の確認が許容応力度計算による場合は、耐震性能等級2以上となっており、2階建て以下の木造住宅で多い壁量計算では耐震性能等級3とされています。
4-3.省エネルギー:断熱等性能等級5、一次エネルギー消費量等級6
住宅の外壁、窓その他の部分からの熱の損失を抑え、一次エネルギー消費の合理化を適切に図るためのものです。2050 年のカーボンニュートラルや脱炭素社会の実現に向けて、認定基準が強化されました。
より断熱性能の優れた住宅にすると共に、消費電力の少ない家電製品で省エネルギー・省資源を図るということですね。
断熱仕様などで初期工事費用は増えますが、光熱費や冷暖房費を節約できるため、長い目で見ればお得になります。
4-4.維持管理・更新の容易性:維持管理対策等級3
ここでは、専用配管の維持・メンテナンスが容易に行える構造とすること、そして定期的な点検を行うことが義務付けられています。
たとえば、給水管・給湯管あるいは排水管などを容易に点検や交換できるような仕組みにしておけば、水漏れや老朽化に伴う交換などにも対応できます。つまり、3世代が引き継いで快適に住み続けられることを前提としているのです。
4-5.可変性:マンションなどの共同住宅(躯体天井高=2.65m)
100年間住み続けることを想定した長期優良住宅では、ライフスタイルや家族構成の変化にも対応できるようにしておかなければなりません。
その場合、間取りを変えても配管や配線などを設置できるように、躯体天井高さを確保しておく必要があります。
なお、躯体天井高さとは、仕上げの床から天井までの高さではなく、構造躯体の床から天井までの高さのことで、マンションなどに適用される基準です。
4-6.バリアフリー:高齢者等配慮対策等級3(共同住宅の共有部分)
バリアフリー性は、戸建て住宅では認定基準の対象にはなっていません。また、マンションなども専用部分ではなく、共用部分のみが対象となっています。
これは、住居内のバリアフリー化は増改築などで容易に行えることに対応したものです。しかし、可能であれば手すりの設置や段差の解消、そしてトイレなどの介護スペースなどには対応しておく方がいいでしょう。
4-7.居住環境
長期優良住宅の場合、居住環境においても気を使わなければいけません。その地域の景観や環境などを乱してはいけないからです。
その地域によって、地区計画や景観計画、条例などによる街並み計画(協定)は異なり、協定の区域内にある場合は、そこのルールを守る必要があります。
たとえば、あなたも隣の家がとても派手な住宅では、不快に思うのではないでしょうか。実際に、京都などの景観が規制されているようなところでは、コンビニなども茶色です。
4-8.住戸面積
快適に生活するためには、ある程度の広さを確保しなければいけません。その条件は、一戸建てと共同住宅によって異なります。以下がその居住面積です。
- 戸建て住宅:75㎡以上
- 共同住宅:40㎡以上
ただ、これはあくまでも基準でしかありません。その他にも、階段部分を除く1階の床面積が40㎡以上なければいけないなどの規定があります。
4-9.維持保全計画
長期優良住宅でも、手入れを行わなければ、寿命の短い住宅となってしまいます。ですから、維持保全計画で長期優良住宅の条件に満たしているのかを定期的(約10年)に点検を行い、必要があれば補修や修繕を行わなければいけません。
維持保全計画では、あらかじめどのように維持保全するかが義務付けられており、主な計画項目は以下になります。
- 構造耐力上主要な部分
- 雨水の浸入を防止する部分
- 住宅に設ける給水または排水のために設備
上記の他に、台風や地震があった場合には、臨時に点検することも求められています。維持保全計画は、家のカルテともいえますね。
4-10.災害配慮
これは、所管の行政庁が定めた措置を講じることとなっています。災害対策などの内容は地域によって異なるため、所管の行政庁で確認するようにしてください。
なお、以上1〜9までの長期優良住宅認定基準の詳細は国交省のホームページで確認することができます。
国交省:優良住宅認定基準
5.認定してもらうための手順
長期優良住宅に認定してもらうには、いくつかの手順を踏まなければなりません。具体的に、どのような手順になるのかをこの項で紹介します。
まず、登録住宅性能評価機関に技術的審査を依頼します。その後、適合証が配布されたら、所管行政庁に認定申請を行い、審査に通ると長期優良住宅として認められ、認定通知書が交付されます。
もちろん、最終的に長期優良住宅として認定されるには、行政の完了(竣工)検査に合格しなければなりません。
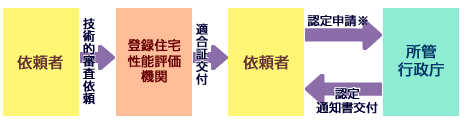
これらの具体的な申請や書類作成は、施工するハウスメーカーや工務店が行ってくれます。しかし、施主が記録・保管しておく、先の維持保全計画もありますので、全体像は知っておいた方がいいでしょう。
その場合、長期優良住宅に関しての詳しい内容は、「長期優良住宅建築等計画の認定申請をされる皆様へ | 一般社団法人 住宅性能評価・表示協会」で詳しく解説しています。気になる方は、こちらにも目を通しておくようにしましょう。
6.長期優良住宅の申請ポイント
ここまで、長期優良住宅について解説してきましたが、申請にはいくつかのポイントがあります。
そこで、この項ではそれらをわかりやすく解説します。これから注文住宅を建てるのであれば、とても参考になるはずです。
6-1.着工前に申請を行う
長期優良住宅の認定を受けるためには、必ず着工前に認定申請を行う必要があります。
もちろん、申請書には設計図書も添付しますから、設計の段階で「長期優良住宅にしたい」ということを担当者に伝えることを忘れないでください。
6-2.長期優良住宅に慣れたハウスメーカー・工務店を選ぶこと
すでに述べたように、長期優良住宅は、設計や申請などに手間と暇がかかります。そのため、全てのハウスメーカー・工務店でも優良住宅の建設に積極的、そして慣れているというわけではありません。
不慣れな住宅メーカーに依頼すると、熱心にはあなたの話を聞いてくれないかもしれません。ですから、長期優良住宅の実績が多いハウスメーカーや工務店を選ぶようにしてください。
一生に一度の買い物だからこそ、あなたの家づくりを、「自分の住宅のように熱心で親身になって担当してくれる工務店」に依頼するようにしてください。
まとめ
長期優良住宅は、性能の高い住宅を3世代まで住み続けられることを目的としています。そのための申請や工事にはいろいろな手間と費用がかかりますが、認定されれば税金などの優遇措置をうけられます。
また、資産価値が上がるため、中古住宅となった場合も一般的な住宅に比べて高く評価されます。
さらに、3世代が引き継いで住み続けるとすると、住宅ローンさえ返済してしまえば、あなたのお子さんや孫は、メンテナンス費用だけで住み続けることが可能なのです。
せっかく夢のマイホームを建設するのであれば、長い目で見て長期優良住宅を目指した家づくりにしてはいかがでしょうか。
住宅は一生に一度の高価な買い物です。数千万円単位になるため、できれば値段を安くしたいものです。
実は値段の高い注文住宅ですが、建売よりも安く家を建てられる方法があるってご存知ですか?
建売でもいいですが、せっかくであれば自由に仕様や間取りを選べる注文住宅がいいですよね。
ただ、注文住宅は失敗してしまう方がほとんどです。夢のマイホームで後悔したくないですよね。
※お断り自由・完全無料